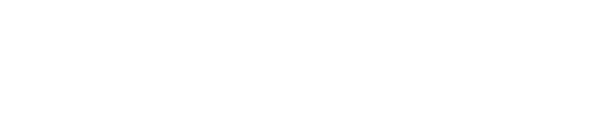ケース2.「クリニックを開業して10年。脳梗塞を発症してしまいました。後遺症が残り、現場に復帰することができません。何とか事業を続けたいのですが……。」40代・開業歯科医師の場合
相談者は、バリバリの働き盛りに不幸にも脳梗塞を発症してしまった
ワハハ歯科医院40代の歯科医師 Tさん です。
「念願のクリニックを開業して10年。まだ法人化はしていないのですが、やっと経営も軌道に乗ってきたところで脳梗塞で倒れてしまいました。クリニック開業時のローンはまだ返済途中ですが、脳梗塞の後遺症で利き手に痺れが残って障害者手帳3級が交付され、歯科医として現場復帰することはできません。しかし、事業は何とか継続していきたいと考えています。既に入っている生命保険を活用することはできるのでしょうか?」
個人でクリニックを開業している医師の方に多いのがこのケース。働き盛りで「まだまだこれから!」という時期に、予期せぬ事態から従来と同じような働き方ができなくなってしまうというものです。この先何年も現役で頑張っていく予定で借入金も残っており、スタッフの賃金なども確保しなくてはならない等、かなり大変な状況です。
他人事ではない脳血管疾患
自分に関係ないと、病気への備えをついつい後回しにしてしまうものですが、日本では毎年およそ10万人が脳血管疾患(いわゆる脳卒中)に罹患しています。大変メジャーな病気と言えます。脳卒中の中でも特に多いのが今回のケースと同じ脳梗塞です。
平成29年のデータによりますと、脳梗塞で亡くなった方は6万人を超え、くも膜下出血の1.2万人、脳出血の3.2万人に比べてかなり高い罹患率となっています。さらに同年の脳梗塞の死亡率は49.8%と、発症した2人に1人は亡くなっているのです。
平成29年(2017年)人口動態統計(確定数)の概況(厚生労働省)より
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei17/dl/11_h7.pdf
幸いなことに一命を取り留めたとしても、その後に後遺症が残ってしまうことも多々あります。平成28年のデータでは、介護が必要となった主な原因の第2位が脳卒中となっています。
平成28年 国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)より
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/05.pdf
このようなデータからも、Tさんのケースは全く他人事ではなく、「明日はわが身」と備えておくことが安心につながることが分かります。Tさんの場合、利き手の親指と人差指にしびれが出る後遺症が残ってしまい、身体障害者手帳の3級が交付されました。
このようなケースで何の備えもしていなかった場合、すぐに歯科医院経営そのものが危機的状況に陥ってしまいます。
クリニックの場合、ケース1の中小企業の社長Mさん同様、院長一人で治療のほぼ全てを請け負っていることが多く見られます。患者さんをどうするのか、スタッフの賃金、クリニックの地代、銀行からの借入金、住宅ローン・・そして自分自身と家族の今後の生活など、問題が山積みとなってしまいます。
このような状態になってしまった後で、新たな生命保険に入って対策を立てることは残念ながら不可能です。幸いなことに、この歯科医師さんには、さまざまなリスクを考慮したある生命保険に数年前に切り替えてもらっていました。具体的にどのような保険なのか、見てみましょう。
定期的にしたい保険の見直し
Tさんとは、私が独立する前からのお付き合いです。10年前に彼がクリニックを開業する際に相談を受け、生命保険に加入していただきました。その保険内容は、当時メジャーだった死亡保険(死亡・高度障害)です。これは死亡時だけではなく、高度障害と認定された時には生前に保険金を受け取ることができるという支払要件のものでした。
<開業当時の保険>
①契約者
本人
②被保険者
本人
③ 保険金額
1億円
④支払要件
死亡時+高度障害時
⑤ 保険期間
65歳
⑥ 受取人
本人
しかし、この保険でカバーできる範囲がとても限られているという問題がありました。あくまで死亡と高度障害になった場合にのみ適用されるものであり、保険会社の約款には国の身体障害者福祉法で定められた障害状態とは違う基準が設けられているのです。例えば、Tさんのように3級の障害者手帳を交付されても、高度障害とは認められず、保険金を受け取ることができないケースもあるのです。
数年前から、このような死亡時の保障がメインの保険から、いわゆる「長生きリスク」に備える保険が生命保険の主流となってきました。そこで3年ほど前に、保障範囲が広い「生活保障型保険」に切り替えることをご提案したのです。以下が具体的な保険内容です。
<保険見直し後>
① 契約者
本人
② 被保険者
本人
③ 保険金額
1億円
④ 支払要件
死亡時・高度障害時+三大疾病+障害(3級以上の障害手帳を持っていること)+介護 (要介護2)
⑤ 保険期間
65歳
⑥ 受取人
本人
生活保障型保険とは、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になってしまった時、また病気やけがで身体に障害が残った時に、収入の減少や治療などで発生する支出の増加に備えることができる、幅広い保障が受けられる保険です。各社によって支払条件は細かく定められているのですが、今回は公的制度と連動している保険をご提案しました。
公的制度と連動した保険とは、身体障害者福祉法によって発行される身体障害者手帳制度と連動した保険を指します。障害状態を自治体が半断して交付された手帳を持ってさえいればいいのです。それによって給付金を受け取ることができるという、大変シンプルで分かりやすいものとなっています。
この保険に切り替えていたおかげでTさんは給付金を手にすることができ、それを当面の運転資金とすることができたのです。
知ってますか?全部で7つ 保険業界共通の高度障害の内容
死亡に無料で付帯されている“高度障害”。 実はこれ保険業界共通の条件です。
“高度”という文言からイメージできる通り、重い障害状態を指します。
しかし、その内容を細かく把握している方はどれほどいるでしょうか?
以下がその一覧です。
高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(公益財団法人生命保険文化センターHPより抜粋)
いかがでしょうか。
一言で、「なかなか無い状況」ではないでしょうか?可能性が限りなく低いから死亡保障に無料付帯できるんです。「高度障害があるから安心」と思っている方がいらっしゃいましたら少し考え直していただいた方が良いかもしれません……
意識すべき保険のトレンド
「長生き損」「長生きリスク」などの言葉を耳にしたことはありませんか? これまでは「長生き=幸せなこと」という価値観が強かったのですが、近年、そのような風潮に大きな変化が起きています。平均寿命が伸び、死亡リスクが減少するにつれ、今度は病気やけがで健康を損なってしまった状態で生活を続けなくてはならないリスクが指摘されるようになってきたのです。
厚労省が公開した「平成29年簡易生命表」によると、日本人の平均寿命が過去最高を更新して、男性は81.09歳、女性は87.26歳となりました。
平成29年簡易生命表より(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/index.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/dl/life17-02.pdf
しかし、これはあくまで平均寿命の調査にすぎません。ここに、健康状態で日常生活を送ることができる「健康寿命」を重ねてみると、以下のようなグラフになります。
平成30年度版高齢社会白書(内閣府)より
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/zenbun/pdf/1s2s_02_01.pdf
2016年の男性の平均寿命は80.98歳、健康寿命は72.14歳。女性の平均寿命は87.14歳、健康寿命は74.79歳。平均すると男性は8.84年、女性ではなんと12.35年も「健康ではない状態」で生活をしていることになるのです。
このような現状に合わせて、最近の生命保険はこの平均寿命と健康寿命の差分にスポットを当てる商品が主流となっています。つまり、健康を損なってしまった状態で長生きをすることになった時の不安をカバーするものにシフトしているのです。
ご自身が入っている生命保険をよく把握し、それが時代に適したものとなっているのか、定期的に見直しをすることが重要と言えます。さらに現在ではIoT機器やウェアラブル端末を使用した「健康増進型」という健康でいれば保険料が安くなるなど、そもそも病気にならないように努力をしましょう!という働きかけも保険業界では加熱しつつあります。